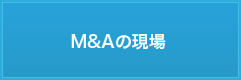会社を売却する真の理由
弊社に持ち込まれるM&A案件は、表面的な売却理由は様々である。
・高齢だが後継者がいない
・病気になった
・早期リタイアしたい
・海外移住したい
・事業に飽きた
・本業に専念したい
・違う事業がしたい
これらの理由の共通項を少々強引にまとめると、“その事業に対する意欲が減退した”ということになるのではないかと思う。
日本では、会社を売却することに対する罪悪感・抵抗感が、まだ根強く残っている。
しかし、経営者が事業意欲を無くした会社が、人口が減少し国内経済が縮小する中で、厳しい競争を果たして勝ち残っていくことができるだろうか?
オーナー経営者が自らの事業意欲減退を認識した場合には、社内外の意欲あふれる個人・会社へ事業を継承する方が、顧客・従業員・社会、そしてオーナー経営者本人にとって、間違いなくプラスとなるはずだ。
この観点からすれば、会社売却は、社会的にもっと肯定的に捉えられるべきだと思う。
(関連トピックスとして、事業意欲と会社の売り時の関係について、M&Aコラムの中の「いつが会社の売り時か」に纏めてあるので、是非、ご参考下さい。)
籠谷
02/Oct.2007 [Tue] 14:36
M&A仲介会社の大義と責務
この2日程、ファミリービジネスの役員会に出席するため、兵庫県に出張に来ている。
ここで耳にしたのが、地元の経営者が会社を売却し、ハッピーリタイアを実現したというニュース。
後継者が不在という典型的な事業承継型M&Aだったようだ。
聞くところによると、彼は、経営者としてのプレッシャーから開放されて、趣味のガーデニングに没頭する穏やかな毎日を過ごしているそうだ。
振り返ると、M&Aの仲介会社を興すと地元の経営者に挨拶に回った時には、我々のビジネスは地元経営者からは好意的には受け入れられなかった。
日本、特に地方では、モノ作りが一番尊く、サービス業は虚業と見られがちだ。特に、M&Aという一見怪しげなことをビジネスにしていると、その傾向が強くなる。
“人の会社を売買して生計を立てるなんてけしからん。はやく、モノづくりに帰ってきなさい。”という意味合いのことを言う経営者までいた。
しかし、冒頭の会社売却を成功させた経営者のように、M&Aにより幸福な結果(雇用の維持・会社経営の安定化・創業者利益の確定)を手に入れた人物が身近に出て来たことにより、周りの態度も変化し始めた。
M&Aへの抵抗感が薄れ、M&A仲介というビジネスも一定の理解を得始めたように思う。
我々は、中小企業のM&Aの仲介というビジネスは、事業承継の円滑化による雇用の維持・会社経営の安定化を通じて、地域社会や日本経済の活性化に貢献する、社会的意義の大きい仕事であると信じている。
そして、その社会的大義を胸に、日々、誇りを持って、業務を行っている。
兵庫県の片田舎で起きた小さな変化は、今、日本各地で起こりつつある流れの一例に過ぎない。
この流れを加速させ大きな潮流に変えていくために、M&Aによる事業承継の意義を世に発信していくことも、また、我々の責務である。
籠谷
13/Sep.2007 [Thu] 14:30
IT企業のM&A
弊社は、ドリームクラスター株式会社と中小IT企業のM&A仲介業務で提携した。
プレスリリースはこちら。
IT業界は、経営者のM&Aに対する抵抗感が少ないこと、また、競争激化・人材不足等、M&Aが活発化する要因を備えている。
この提携により中小IT企業のM&Aを、より効率的・効果的にサポートして行きたい。
籠谷
06/Sep.2007 [Thu] 14:26
業務提携近況
税理士・会計士事務所との業務提携を開始して1ヶ月強、引き合い先は30件を超え、業務提携契約を締結して頂いた事務所も20件弱となった。当初は、月10件ぐらいのペースを想定していたため、計画以上のスピードで提携が進んでいることになる。
これは、弊社の提案する提携内容が提携先事務所様にとって非常にメリットのあるものとなっていること、及び、中小企業のM&Aに対応する必要性を多くの会計士事務所様が認識し始めていること、が主な要因だと思われる。
少子高齢化の影響を受け、事業承継絡みのM&Aは増加を続けている。
この状況を反映して、最近では、M&Aコンサルティングをサービスラインの一つにしている会計事務所も多い。
確かに、M&A関連の税務サービス・株価評価・デューディリジェンス等は、勉強熱心な税理士・会計士の先生方ならば、十分に対応可能だ。
一方で、弊社の主要業務である売り手と買い手のマッチングは、税務業務の副業という位置づけでは適切に対応できないと思われる。
マッチングの背後には、業界分析・買い手とのネットワーキング・要望把握等の作業があり、これが相当時間を要するからだ。
弊社と提携して頂くことで、提携先事務所様は、弊社のノウハウ・ネットワークを活用したM&A専門会社レベルのM&Aサービスを提供でき、また、貢献度に応じてM&Aサービスの対価を受け取ることができる。
弊社の提携内容は、各事務所様にとって、メリットの高いものだと自負している。
より多くの会計・税務事務所と提携頂けるよう、提携内容を改善していくとともに、弊社のブランド力を高めていくよう、今後とも努力していきたい。
籠谷
02/Sep.2007 [Sun] 14:23
秘密保持の責任
日々業務を行っている中で、他のM&Aの仲介業者の秘密情報の管理状況が心配になることがある。数は少ないが、仲介業者・個人ブローカーが、秘密情報を簡単に他人に教えてしまうケースを散見するからだ。
会社譲渡や会社売却に関する情報開示は非常に繊細な問題で、従業員、取引先、銀行への情報開示はしっかりとコントロールしておかないと、その譲渡自体が白紙になるのみならず、本業にも悪影響を及ぼしかねない重要な事項である。
弊社は、当然ながら、秘密保持には最大限の注意を払っている。
会社様から秘密情報を提出して頂く際には、基本的に秘密保持契約を締結させて頂き、法律的に自らに縛りをかけている。
会社売却・事業譲渡は、オーナー経営者様の人生に何度もない大切なイベントであり、このイベントを問題なく安全に完了できるようサポートすることが、当社の使命である。
会社様の信頼に応えるため、より一層情報管理を徹底しようと決意を新たにする次第である。
籠谷
27/Aug.2007 [Mon] 14:21