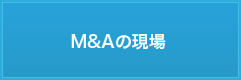中小企業のエムアンドエー(MアンドA)マーケットの変遷
本日、面談をしたある買い手企業の社長から、「最近、新手のM&A仲介会社が増えてきましたね。」というコメントを頂きました。
たしかに、最近、聞いたことがないような同業退社のHPを目にしたり、社名を耳にする機会が増えています。
業界でのプレイヤーが増えることで競争は厳しくなりますが、その分業界全体の知名度や多様性が高まるため、業界内の他のプレイヤーにとってもメリットはあると思っています。
一方で、M&A仲介会社の大量出現は過去に何度も起こっており、そのたびにほとんどの会社が淘汰されるというサイクルが繰り返えされているのも事実です。
歴史を振り返れば、1990年以前は、日本のエムアンドエーといえば大企業が中心で、アドバイザーの仕事も大手証券会社や銀行の独壇場でした。
その中でも、山一証券のM&Aアドバイザリー部門は営業力が強く、かなりの案件獲得数を誇っていました。
この山一証券のM&A部門から飛び出したOBが、多くの独立系のM&Aアドバイザリー会社を創業しており、M&Aアドバイザリー業界の裾野拡大に貢献しました。独立系M&Aアドバイザリーファームの最大手で、M&A情報提供サービスも手掛けるレコフも山一OBの創業です。
ただ、証券会社OBによる独立系のファームも、比較的大規模な案件を中心に業務を行っており、いわゆる中小企業のエムアンドエー(MアンドA)はこの時代はまだ一般的ではありませんでした。
その後、1991年に中小企業のM&A仲介をする目的で、現在M&A仲介会社で唯一の上場企業である日本M&Aセンターが設立されました。
この日本M&Aセンターを筆頭に、1990年代に中小企業のM&A仲介を専業とする会社がいくつか生まれ、中小企業のエムアンドエー(MアンドA)マーケットが形成されていきました。
とはいえ、1990年代は、中小企業の経営者にエムアンドエー(MアンドA)が浸透しておらず、またバブル崩壊の影響もあり、中小企業のエムアンドエー(MアンドA)市場は2000年代初頭まで、それほど拡大しませんでした。
現在、M&A仲介会社の最大手として売上高72億円を誇る日本M&Aセンターも、創業から11年が経過した2002年時点の売上高は4億円に過ぎませんでした。
1990年代のM&A仲介マーケットの草創期に設立された会社で、現在も第一線で活躍している会社は、日本M&Aセンターを含む数社に過ぎず、多くが消滅しています。
このように1990年代から2000年代初頭まで、徐々に形成されてきた中小企業のエムアンドエー(MアンドA)マーケットですが、2002年以降は状況が激変します。
2002年から2008年まで続いた戦後最長の景気拡大期間である「いざなみ景気」の影響もあり、国内では空前のM&Aブームが到来したのです。
大型のM&A案件も活発でしたが、中小企業の事業承継の解決策としてM&Aの認知度が高まり、中小企業のM&A件数もうなぎ上りに増加しました。
さらに、2006年には日本M&Aセンターが東証マザーズに上場し、2007年には中小企業のM&A仲介業界は加熱のピークを迎えます。
この爆発的に市場が拡大した2004年~2008年の間に、雨後の竹の子のごとくM&A仲介会社が乱立しました。
完全に独立系の会社に加え、コンサルティング会社や会計事務所が一事業部として新規参入するケースなど、毎週数社は新会社が出てくるような状況でした。
このように急拡大し、活況を呈した中小企業のエムアンドエー(MアンドA)マーケットですが、2008年のサブプライム、2009年のリーマンショックをきっかけに、急速に冷え込みます。
市場の縮小に合せて、中小のM&A仲介会社が次々と廃業していきました。
特に、M&A専業でないコンサルティング会社や会計事務所は事業部を閉鎖するか開店休業状態になっているところが多くありました。
ちなみに、弊社インテグループもこの時期(2007年)の創業です。
同業が乱立し競争は確かに激しかったのですが、当時は珍しかった完全成功報酬制がお客様から評価され、独自のポジションを確立できたことで、無事生き残ることができました。
弊社と同時期に創業した会社で今も活躍している会社を見てみると、「M&A専業」、「独自性」、「信念」という3つの特徴があります。
流行っているからと本業の傍らで副業的に手を出した会社、独自の売りや事業モデルがない会社、M&Aについて何の思い入れもなく儲かりそうという理由だけで参入した会社は、目立った結果を残せずに知らぬ間にいなくなっていました。
その後、リーマンショックの影響が薄れ始めた2011年以降は、中小企業のM&Aマーケットも復調しており、冒頭の社長がおっしゃたとおり、新規参入がまた活発化してきています。
ただ、これまでの何度も繰り返されたように、しっかりとしたビジネスモデルと事業理念がない多くの会社が消え去り、数社のしっかりとしたプレイヤーだけが市場に残ることでしょう。
日本では2012年より団塊の世代が65歳を超え始め、この世代の経営者の事業承継問題は今後ますます深刻化していきます。
M&Aはこの事業承継問題解決の有力な選択肢の一つであり、今後少なくとも5年間は中小企業のエムアンドエー(MアンドA)マーケットは拡大するとみられています。
そして、市場の拡大に伴い、新規参入や新サービスが次々と現れ、過去20数年がそうだったように、次々と退場していくでしょう。
2007年の創業当時はエムアンドエー(MアンドA)マーケットの新参者だった弊社ですが、設立7年目の今は、相応の実績と認知度を有するマーケットの構成員の1社になれたのではないかと思っています。
その自負と責任感を持って、今後も繰り返されるであろう市場の選別に淘汰されないように、しっかりとしたサービスを提供し続けたいと思います。
関連記事>エムアンドエー(MアンドA)アドバイザーの選び方
関連コラム>M&A仲介会社の見分け方
トップページ>中小企業M&A仲介のインテグループ
04/Jun.2013 [Tue] 13:22
中小企業のM&Aにおける買収の成否の評価
以前会社の売却をお手伝いをした社長様から、本日久々にご連絡を頂き、近況を伺うことができました。
社長によると、買い手企業との新製品の共同開発や、海外市場でのジョイントベンチャーの設立等、買収後に様々な成果が出ており、買い手からも買収は成功だったとの評価をもらっているようです。
微力ながらお手伝いをさせていただいたアドバイザーとしては、大変うれしく思います。
本件は、会社は小規模ながらニッチ市場でトップシェアを誇っており、経営手腕に優れた創業社長が買収後も一定期間取締役として残ることが条件となっていましたので、買収後もうまくいくと当初から確信があり、それほどおどろきもありませんでした。
しかし、本日お聞きしたお話は、中小企業のM&Aにおける「買収成功」と「買収失敗」はどのように判断するべきなのかということについて、改めて考える機会になりました。
M&Aの書籍には、「買収の多くは失敗している」というような記述がよくあります。
では、買収の失敗とは、どのような状態を指しているのでしょうか?
実は、「買収失敗」の定義は容易ではありません。
例えば、買収の失敗例として、買収後に、株価が下がった、利益が下がった、のれんの減損損失が発生した、財務が悪化したという指摘がなされることがあります。これは、買収後のネガティブな結果に着目した指摘です。
しかし、買収後にネガティブな結果が出た場合に、それだけをもって失敗だった結論して良いのでしょうか?
例えば、もし買収しなければ、その会社がライバル企業に買収されることで、大きくシェアを失い、買収した場合と比べて、より一層利益が減ってしまうというケースも考えられます。
インフルエンザの予防注射の副作用で体がだるくなった場合に、副作用が出たことのみをもってインフルエンザは失敗だったとは言わないでしょう。
予防注射によって、インフルエンザの罹患という、よりネガティブな結果を回避できている可能性があるからです。つまり、結果がネガティブだから買収は失敗とは必ずしも言えないということです。
実際に、競合会社の買収を阻止・妨害することを目的とした買収提案や買収金額のつり上げは、M&Aの世界ではよく行われています。この観点からいうと、買収の成否を厳密に評価しようとすれば、買収した場合としなかった場合の両方のケースについて結果を比較する必要があり、これはタイムマシンでもない限り不可能です。
また、買収時に策定した計画を達成したかどうかで、買収の成否を判断するという考え方もあります。
買収する際には明確な目的とそれに基づいた計画が存在するはずであり、その計画が達成できれば成功、できなければ失敗と判断するわけです。
この考え方は、目的と結果の比較による評価であり、一見合理的に思えます。
しかし、現実には、目的は未達だが一定の成果はあったというケースは少なくなく、このような場合も失敗としてしまうのは、評価が厳しすぎる気がします。
また、買収計画は、どうしても背伸びをしたものになりがちで、そのような達成困難な目標に到達できなかったからといって失敗だと結論するのは少し乱暴です。
また、計画との比較という方法論の最大の問題は、財務状態(貸借対照表)の視点が抜け落ちやすいことです。
つまり、損益計画は達成しているが、買収の際の多額の借入で財務が悪化しているような状態は、本当に成功と言えるのかということです。
上記を勘案すると、中小企業のM&Aにおける買収の成否は、買収による投資額を回収できたかどうかで評価するのが、最も現実的かつ効果的だと思います。
買収に投下した金額が数年以内に回収できたのであれば、買収は成功した、少なくとも、失敗していないといえるでしょう。
買い手が中小企業の場合、買収によるリターンの高さよりも、買収により自社が傾かないかという安全面を気にする経営者が多く、回収できたかどうかで買収の成否を判定する考え方は、経営者の実感と合致する部分が多いと思います。
中小企業のM&Aの現場では、企業価値評価方法として、買収金額の回収年数を重視した「年買法」という手法が最も一般的に使用されています。
現状の相場観では、年買法における回収見込年数は2年~3年程度で、これは、多くの経営者が、「買収金額としては2~3年で回収できる額が適正である」、換言すると、「投資額が2~3年で回収できるのであればその買収は成功である」、と考えていることを示しているといえます。
買収成功を投資金額の回収と定義すれば、そもそも2~3年で回収できる金額が相場として浸透している中小企業M&Aの現状を考えると、M&Aの書籍がいうところの「多くの買収が失敗」とは逆に、大半のケースが成功の範疇に入ってくるのではないかと思います。
籠谷智輝
22/May.2013 [Wed] 14:19
優秀な企業内M&A担当者の要件③
優秀な企業内M&A担当者の要件の第三の要件です。
(第一の要件については、こちらをご覧ください)
(第二の要件については、こちらをご覧ください)
③売り手社長への敬意を持っている
買い手の方が上だという誤った認識をしている担当者が稀にいらっしゃいます。
確かに、一般的には、買い手の方が売り手よりも会社規模は大きいでしょう。
しかし、売り手の社長は、小さいながらエムアンドエー(MアンドA)の対象となるようなしっかりとした会社を経営してきた方です。
会社の規模や上場しているかどうかは関係なく、相応の敬意を示すのがビジネスマンとして当然だと思います。
なにより、担当者の敬意の無さは、表面上いくら取り繕っていても、面談や交渉の中で滲み出し、売り手社長に伝わってしまいます。
それは、特に、トップ面談時の質問の仕方に現れます。
粗探しのような質問を、ずけずけと、しかも、担当者本人は失礼であるという自覚なくしてしまい、売り手社長の不興を買うのです。
もちろん、M&Aを実行する前に、リスクや疑問点は徹底的に調査・解消すべきですが、売り手社長に対する尊敬の念があれば、質問の仕方も、柔らかく、好意的なものになるはずです。
質問が粗探しのように響くのは、担当者の心底に「買ってやるんだ」という上から目線があるからです。
中小企業のM&Aにおいては、売り手社長は金額だけで相手を選びません。
面談時の印象が悪ければ、いくら良い条件を提示しても、断られてしまいます。
トップ面談の後に、売り手再度から、断りが入るのはよくある話です。
結局、売り手の社長への敬意がなければ良い買収機会を逸してしまうのです。
私の経験上、優秀なM&A担当者は、対象会社のビジネスや社長の考え方を、まず褒めます。
そして、ポジティブな文脈の中に、きわどい質問をうまく織り交ぜて、聞きくべきことをうまく引き出します。
また、トップ面談時には、かならず社長か役員クラスの上席者を連れてきます。
これも、規模は小さいとはいえ一国一城の主である売り手社長への敬意の表れです。
会計・法律の知識がある人物よりも、売り手社長に敬意を払える担当者の方が、M&Aの担当者としてはよほど優秀だと思います。
籠谷智輝
02/Apr.2013 [Tue] 12:12
優秀な企業内M&A担当者の要件②
優秀な企業内エムアンドエー担当者の要件の第二の要件です。
(第一の要件については、こちらをご覧ください)
(第三の要件については、こちらをご覧ください)
②質問の優先順位が適切である
案件についての質問の順序で、担当者のエムアンドエーの経験値が概ね分かります。
案件を紹介を受けた場合には、まずは、ビジネス面での親和性を検討し、その上で財務面で問題ないかを見ていくというのが、一般的な流れです。
したがって、案件の情報が提示された際に、まず最初に聞くべきは、そのビジネスについて質問(ビジネスモデル・収益性・顧客・強み・弱み・特徴・競合)です。
財務面ももちろん重要ですが、初期の段階では、概要資料に記載のある重要ポイント(売上規模、純資産額、有利子負債の額、利益率、売却希望金額等)さえ抑えておけば十分でしょう。
ところが、経験の浅いM&A担当者は、質問の焦点が、最初から財務の細かい部分に行ってしまうことがあります。
特に、財務・経理部の方がM&A担当者となっている場合には、ご自身の得意分野ということもあって、初期の段階から財務諸表の非常に細かい部分質問をしてきます。
財務面に全く問題がない健全な会社であっても、自社のビジネスにとって親和性がないのであれば、買収対象とはなりえません。
したがって、最初に精査すべきなのは、売却対象会社のビジネス面なのです。
財務面については、初期の時点では、大きな問題がないかを確認しておけば十分であり、会計科目の細かい内容まで把握する必要はありません。
(蛇足ですが、最初から財務の細かい質問をしてくる会社ほど、後になってビジネス面でのシナジーがないという理由で見送りとなることが多いです。)
また、質問の優先順位がつけられない担当者は、売り手社長との初回のトップ面談の際にも、非常に細かい財務諸表についての質問を浴びせて、売り手社長の心象を悪くしてしまうこともあります。
トップ面談は売り手社長から直接話が聞ける折角のチャンスなのですから、ビジネス・従業員・企業文化についてのお話しを聞き出すことに集中すべきです。
財務についての財務に関する質問は、あとから書面のやりとりでも十分対応可能なのです。
籠谷智輝
07/Mar.2013 [Thu] 12:05
優秀な企業内M&A担当者の要件①
エムアンドエー(MアンドA)が経営上の重要な手段として定着してきたせいか、最近では上場企業を中心に、社内にM&A担当者をおく会社が増えてきています。
とはいえ、M&A経験者の数はまだ少なく、エムアンドエー未経験の担当者も少なくなく、そのレベルは千差万別です。
そこで、優秀な企業内M&A担当者の要件を、何回かに分けて記載したいと思います。
①レスポンスが早い
優秀な担当者は、案件を進める場合でも、見送る場合でも、とにかくレスポンスが早いです。
良い案件は、当然複数の買い手候補が競合しますので、のんびりしていると他社に案件を持って行かれてしまいます。
検討に値する案件を紹介されたら、できるだけ早く次のステップに進む必要があります。
レスポンスの早い会社の特徴としては、エムアンドエーに関する初期段階の意思決定者(社長又は担当取締役クラス)が明確化されており、M&A担当者が意思決定者に対して、心理的・物理的にすぐにアクセスできることです。
M&A担当者が対応スピードの重要性を理解している場合は、たとえ大企業であっても、紹介して2、3日で必ず連絡があります。
また、見送りの場合も、早急に回答するべきです。
紹介者であるM&A仲介会社に対して申し訳ないと思うのか、見送りの回答を引き延ばす担当者がいますが、これは仲介会社にとっては「ありがた迷惑」な対応です。
我々M&A仲介会社にとっては、検討中という宙ぶらりんな状態が一番困るので、見送りの回答が早い担当者の方が付き合いやすいのです。
その結果、今後の案件紹介がしやすくなり、そのような担当者にはより多くの案件が集まることになります。
籠谷智輝
28/Feb.2013 [Thu] 18:21