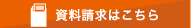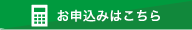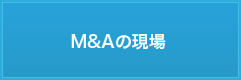中小企業のM&Aにおける買収の成否の評価
以前会社の売却をお手伝いをした社長様から、本日久々にご連絡を頂き、近況を伺うことができました。
社長によると、買い手企業との新製品の共同開発や、海外市場でのジョイントベンチャーの設立等、買収後に様々な成果が出ており、買い手からも買収は成功だったとの評価をもらっているようです。
微力ながらお手伝いをさせていただいたアドバイザーとしては、大変うれしく思います。
本件は、会社は小規模ながらニッチ市場でトップシェアを誇っており、経営手腕に優れた創業社長が買収後も一定期間取締役として残ることが条件となっていましたので、買収後もうまくいくと当初から確信があり、それほどおどろきもありませんでした。
しかし、本日お聞きしたお話は、中小企業のM&Aにおける「買収成功」と「買収失敗」はどのように判断するべきなのかということについて、改めて考える機会になりました。
M&Aの書籍には、「買収の多くは失敗している」というような記述がよくあります。
では、買収の失敗とは、どのような状態を指しているのでしょうか?
実は、「買収失敗」の定義は容易ではありません。
例えば、買収の失敗例として、買収後に、株価が下がった、利益が下がった、のれんの減損損失が発生した、財務が悪化したという指摘がなされることがあります。これは、買収後のネガティブな結果に着目した指摘です。
しかし、買収後にネガティブな結果が出た場合に、それだけをもって失敗だった結論して良いのでしょうか?
例えば、もし買収しなければ、その会社がライバル企業に買収されることで、大きくシェアを失い、買収した場合と比べて、より一層利益が減ってしまうというケースも考えられます。
インフルエンザの予防注射の副作用で体がだるくなった場合に、副作用が出たことのみをもってインフルエンザは失敗だったとは言わないでしょう。
予防注射によって、インフルエンザの罹患という、よりネガティブな結果を回避できている可能性があるからです。つまり、結果がネガティブだから買収は失敗とは必ずしも言えないということです。
実際に、競合会社の買収を阻止・妨害することを目的とした買収提案や買収金額のつり上げは、M&Aの世界ではよく行われています。この観点からいうと、買収の成否を厳密に評価しようとすれば、買収した場合としなかった場合の両方のケースについて結果を比較する必要があり、これはタイムマシンでもない限り不可能です。
また、買収時に策定した計画を達成したかどうかで、買収の成否を判断するという考え方もあります。
買収する際には明確な目的とそれに基づいた計画が存在するはずであり、その計画が達成できれば成功、できなければ失敗と判断するわけです。
この考え方は、目的と結果の比較による評価であり、一見合理的に思えます。
しかし、現実には、目的は未達だが一定の成果はあったというケースは少なくなく、このような場合も失敗としてしまうのは、評価が厳しすぎる気がします。
また、買収計画は、どうしても背伸びをしたものになりがちで、そのような達成困難な目標に到達できなかったからといって失敗だと結論するのは少し乱暴です。
また、計画との比較という方法論の最大の問題は、財務状態(貸借対照表)の視点が抜け落ちやすいことです。
つまり、損益計画は達成しているが、買収の際の多額の借入で財務が悪化しているような状態は、本当に成功と言えるのかということです。
上記を勘案すると、中小企業のM&Aにおける買収の成否は、買収による投資額を回収できたかどうかで評価するのが、最も現実的かつ効果的だと思います。
買収に投下した金額が数年以内に回収できたのであれば、買収は成功した、少なくとも、失敗していないといえるでしょう。
買い手が中小企業の場合、買収によるリターンの高さよりも、買収により自社が傾かないかという安全面を気にする経営者が多く、回収できたかどうかで買収の成否を判定する考え方は、経営者の実感と合致する部分が多いと思います。
中小企業のM&Aの現場では、企業価値評価方法として、買収金額の回収年数を重視した「年買法」という手法が最も一般的に使用されています。
現状の相場観では、年買法における回収見込年数は2年~3年程度で、これは、多くの経営者が、「買収金額としては2~3年で回収できる額が適正である」、換言すると、「投資額が2~3年で回収できるのであればその買収は成功である」、と考えていることを示しているといえます。
買収成功を投資金額の回収と定義すれば、そもそも2~3年で回収できる金額が相場として浸透している中小企業M&Aの現状を考えると、M&Aの書籍がいうところの「多くの買収が失敗」とは逆に、大半のケースが成功の範疇に入ってくるのではないかと思います。
籠谷智輝
22/May.2013 [Wed] 14:19